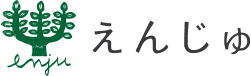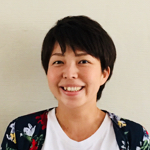アフターケア
事業全国ネットワーク
「えんじゅ」とは
設立に至る経緯
近年、社会的養護の退所者支援の必要性がうたわれ、アフターケア事業が社会的養護において欠かすことのできない支援として位置づけをされ始めています。
しかし、安定した支援を提供するための制度は未だ十分ではなく、アフターケアを担う多くの事業所が不安定な運営基盤のもとで事業を行っています。各都道府県に1ヵ所という体制が多いことから、孤立や孤独感を感じている事業所も少なくありません。
この現状を少しでも改善すべく、社会的養護のアフターケアに取り組む団体で構成する全国ネットワーク「えんじゅ」を立ち上げることといたしました。
各地でアフターケア事業を担う団体同士がつながり、想いや情報を共有し、共に学び、支え合うことで、社会的養護のもとを巣立った方、困難な状況にある方々へ、適切かつ多様な支援を提供できること。アフターケアを担う私たちが高い専門性を有し、健全で豊かな心を持って支援事業を継続できることが、設立の目的です。
社会的養護を巣立った後の課題
社会的養護を必要とする子どもたちの多くが、虐待や貧困などによる深い心の傷をおっています。抱えているトラウマによって、施設を巣立ったのちも、社会生活や対人関係を円滑に築くことができない場合もあります。
親や親族を頼れないことから、保証人の問題をはじめとする、社会生活を営むうえでの様々な手続きが滞ることも少なくありません。経済的な理由等から、大学や短大、専門学校など上級学校への進学率も低く(母子世帯、生活保護世帯よりも低い就学率)、就労するうえで大きなハンデとなっています。
地縁・血縁を重んじ、家庭が円滑に機能していることを前提とした日本社会において、親家族を頼ることのできない社会的養護の退所者たちは、自己責任という名のもと、身に降りかかる全ての課題を自らで解決することを強いられています。
施設や里親など社会的養護の下を巣立った子どもたちが、困った時には安心して助けを求められる「アフターケア」の仕組みが必要であるとともに、日本社会が、施設を巣立った方のみならず、困難な状況にある方たちを、いかに社会で支えていくかを抜本的に見直す時期がきていると思います。
通称名「えんじゅ」の由来
名称の「えんじゅ(槐樹)」とは、もともと薬木として利用され、公害にも強いため日本全国で街路樹として育っている樹木です。全国に育つえんじゅの木のように、アフターケア事業所が、困難を抱えた方々の止まり木、宿り木となり、えんじゅの道を全国につなげ、広げていきたいと願っています。